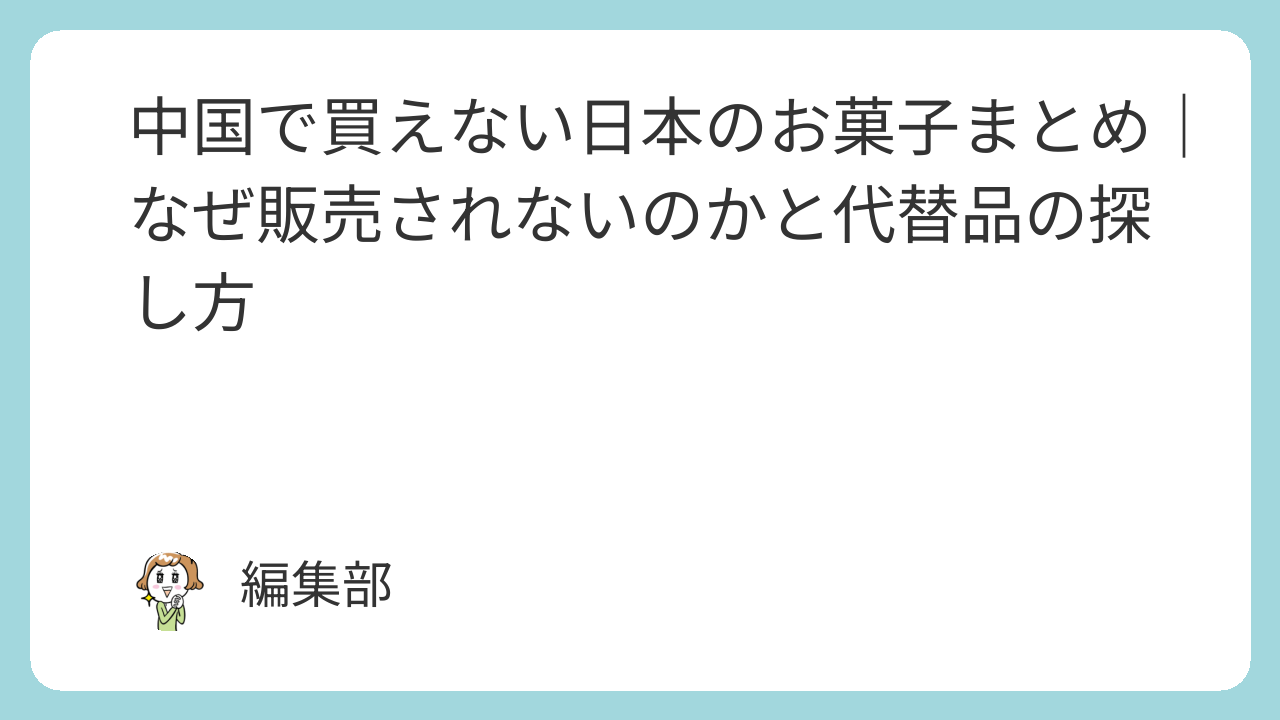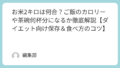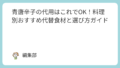日本のお菓子と中国市場の関係
日本のお菓子は品質の高さや豊富なフレーバーで、世界中で人気があります。特にチョコレートやスナック菓子、和菓子などは日本ならではの繊細な味わいが評価されており、観光客のお土産としても高い人気を誇ります。中国でも日系スーパーや輸入食品店を中心に、多くの日本のお菓子が販売されており、若者を中心に「日本のお菓子=おしゃれで高品質」というイメージが定着しています。しかし、中には「中国では手に入らない日本のお菓子」も存在します。たとえば、地域限定のお土産菓子や季節限定商品は現地に流通しにくく、旅行者でなければ購入できないことが多いのです。なぜ人気のある日本のお菓子が中国市場に並ばないのか。その背景を探ると、食品規制や流通コスト、現地需要、さらにはブランド戦略など複数の要因が絡んでいることが分かります。

本記事では、中国で買えない日本のお菓子の具体例や、その背後にある理由を分かりやすく紹介するとともに、現地で楽しめる代替品や実際の入手方法についても詳しく解説していきます。
先に結論をお伝えします
結論として、中国で買えない日本のお菓子が存在するのは事実です。ただし、それは必ずしも「危険だから輸入できない」という意味ではありません。背景には食品添加物や原材料に関する規制の違い、輸入時にかかる関税や物流コスト、さらには現地市場での需要と供給のバランスといった、ビジネス上の要因が複雑に絡み合っています。場合によっては、企業があえて現地販売を見送るケースもあり、それが「中国では手に入らない」という状況を生んでいるのです。また、中国では一部の商品が正規ルートで流通していない場合でも、越境ECや大都市にある日系スーパーを利用すれば意外と簡単に入手できることもあります。つまり「中国で買えない=絶対に手に入らない」というわけではなく、購入方法を工夫すれば十分に楽しむことが可能です。さらに近年では、旅行者や在留邦人がSNSで情報をシェアすることで、入手ルートが広がっている点も見逃せません。結論としては、買えない理由は多岐にわたるものの、工夫や努力次第で味わうチャンスはいくらでもある、というのが実情です。
中国で買えない日本のお菓子の例
以下の表は、中国で買える日本のお菓子と買えない日本のお菓子を比較したものです。
| カテゴリ | 中国で買える日本のお菓子 | 中国で買えない/買いにくい日本のお菓子 |
|---|---|---|
| チョコレート | 明治ミルクチョコ、キットカット抹茶 | 明治THE Chocolate、限定高カカオシリーズ |
| スナック | 定番ポッキー(チョコ・いちご)、プリッツ(サラダ味) | 地域限定ポッキー、プリッツ(たこ焼き味など) |
| 和菓子系 | 一部のどら焼きや大福(冷凍) | 白い恋人、東京ばな奈、萩の月 |
| 季節限定 | ハロウィン・クリスマス仕様のキットカット | 期間限定の地域特産フレーバー |
なぜ中国で買えないのか?
中国で一部の日本のお菓子が販売されない背景には、以下のような複数の要因があります。単純に「人気がないから」ではなく、制度や経済、物流などのさまざまな事情が影響しています。
- 食品添加物や原材料の規制の違い
中国の食品安全基準は日本と異なり、一部の添加物や原料は認可されていないことがあります。そのため、特定のレシピで作られたお菓子は輸入許可が下りない場合があります。特にチョコレートやスナック菓子には保存料や香料が多く使われるため、基準の差が流通制限の大きな原因となっています。 - 輸入コストや関税の高さ
お菓子は単価が安いため、輸入時の関税や物流コストを加えると販売価格が高騰し、現地消費者に受け入れられにくくなります。例えば、日本で100円程度で買える商品が、中国に入ると3倍近い価格になるケースも珍しくありません。こうした価格差は、現地消費者が購入をためらう大きな理由となります。 - 中国メーカーとの競合
中国市場には地元メーカーが製造する類似品が多数存在し、あえて輸入しなくても需要を満たせるケースがあります。しかも現地メーカーは中国人の嗜好に合わせた味付けやパッケージを採用するため、日本ブランドよりも人気を集めることさえあるのです。 - 流通網の制限
特にチルド保存や冷凍が必要なお菓子は、現地の流通環境が整わず販売が難しいことも理由の一つです。冷凍保存が必要な和菓子やケーキ系のお土産菓子は、輸入段階でコストが跳ね上がり、結果として販売が見送られる場合があります。都市部では改善傾向にありますが、地方都市ではまだインフラが追いついていないのが現状です
中国で手に入れる方法
「現地で売っていない」とはいえ、工夫すれば中国でも日本のお菓子を楽しむことができます。入手経路を工夫することで、日本に行かずとも意外と選択肢は豊富にあります。
- 越境ECサイトを利用する
天猫国際、京東(JD Global)、Amazonグローバルなどの越境ECでは、日本から直接配送されるお菓子を購入できます。中には限定フレーバーや季節商品も取り扱っており、在庫状況をチェックすれば日本に近いラインナップを楽しめます。価格はやや高めですが、正規品を手に入れたい人に向いています。 - 日本旅行や空港免税店で購入する
観光や出張で日本を訪れた際にまとめ買いして持ち帰るのも一般的な方法です。特に空港免税店では通常より安く購入できるケースがあり、ばらまき用のお土産を確保するのに便利です。また、地域限定のお菓子もこの方法なら確実に入手できます。 - 中国国内の日系スーパーや輸入食品店
大都市を中心に日系スーパーがあり、人気の日本お菓子が期間限定で入荷することがあります。定番商品に加え、日本からの直輸入キャンペーンを実施する場合もあり、情報をチェックしておくと掘り出し物に出会えることもあります。 - SNSや代購サービスを活用する
WeChatや小紅書(RED)などのSNSを通じて、日本から輸入して販売する「代購(だいこう)」を利用する人も多いです。信頼できる代購を選べば、限定版や地方限定のお菓子も現地で手に入る可能性があります。
中国で人気の「似て非なる」お菓子
中国では、日本のお菓子に似た商品が多く販売されています。日本ブランドが公式に販売していないフレーバーやデザインを、中国メーカーが独自に展開しているケースもあり、消費者にとっては「本家そっくりだけど微妙に違う」という体験が楽しめる市場になっています。
- ポッキーそっくりのお菓子:「百奇(バイチー)」というブランド名で販売されており、パッケージも味もポッキーに近いです。近年では抹茶味やマンゴー味など、日本でもあまり見ないフレーバーを追加しており、オリジナリティも出ています。
- 日本風せんべい:塩味や海苔味をベースにした中国メーカー製のスナックがあり、日本の味をイメージさせます。中には醤油風味を強めたものや、ピリ辛風にアレンジされたものもあり、中国人の好みに寄せてローカライズされている点が特徴です。
- 抹茶味のお菓子:日本からの影響で抹茶フレーバーのお菓子は大人気。中国メーカーも積極的に商品化しており、クッキーやキャンディー、さらにはアイスクリームまで幅広く展開されています。パッケージも日本風のデザインを取り入れ、見た目から日本らしさを強調している商品が目立ちます。
- その他の類似品:ハイチュウに似たソフトキャンディや、日本のプリッツ風のスティック菓子なども市場に並んでいます。どれも本家に似せつつも、中国人の味覚に合わせて甘さや香りを調整しており、まさに「似て非なる」存在といえるでしょう。
旅行者向けのお土産アドバイス
日本から中国に帰国する際のお土産として日本のお菓子を選ぶ場合、以下の点に注意すると良いでしょう。日本のお菓子は見た目も華やかで話題性があるため、お土産として渡すと喜ばれることが多いですが、選び方ひとつで印象が大きく変わります。
- 常温保存ができるものを選ぶ:東京ばな奈や白い恋人などは人気ですが、夏場は溶けやすいチョコレートより焼き菓子がおすすめです。保存のしやすさを考えると、クッキーやせんべい、パイなども重宝されます。移動時間が長い場合や中国の暑い地域へ持ち帰る場合には、冷蔵が不要なタイプを優先すると安心です。
- 小分け包装が便利:中国ではシェア文化が強いため、職場や友人に配りやすい小分け包装のお菓子が喜ばれます。さらに、パッケージに日本語が記載されていると「本場のお菓子」という特別感が演出でき、話題作りにもなります。見た目がかわいいデザインや季節限定パッケージは特に人気が高いです。
- 中国未発売の商品を選ぶ:現地で手に入りにくい商品を選ぶと特別感があります。特に地域限定のお菓子や季節限定フレーバーは「日本でしか買えない」というプレミア感が強く、喜ばれるポイントです。たとえば北海道限定のラングドシャや京都の抹茶菓子などは高い人気を誇ります。
- 賞味期限にも注意する:せっかくのお土産でも賞味期限が短すぎると渡すタイミングを逃す場合があります。1週間以上日持ちするものを選ぶと安心です。
まとめ
中国では、安全規制や輸入コスト、現地需要などの影響で買えない日本のお菓子が存在します。しかし、それは必ずしも「危険だから流通していない」というわけではなく、むしろビジネス的な要因や市場の特性が大きな要因となっています。たとえば、輸送コストが高すぎて採算が取れない場合や、現地の消費者ニーズに合わないと判断された場合には、企業側が販売を見送るケースも多いのです。一方で、越境ECや旅行を活用すれば入手は可能であり、さらに現地でしか味わえない中国独自のお菓子と日本のお菓子を食べ比べるのも楽しみ方のひとつになります。このように双方を比較することで、それぞれの文化が生み出す味やパッケージデザインの違いを理解でき、食の多様性や国ごとの嗜好の差をより深く実感できるでしょう。